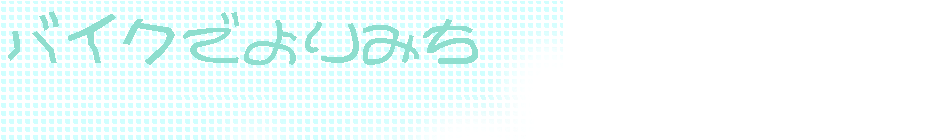夏バテの原因は外と冷房の気温差
夏の終わりに多くの人が経験する症状が夏バテですが、必ずしも夏の終わりだけに起こるわけではありません。
夏バテを起こす条件が揃えば、いつでも起こるリスクがあります。
夏バテになると、強い疲労感やだるさ、また食欲が低下するなどの症状が起こります。
熱があるというわけではないけれど、だるい感じが長く続き、やる気が起こらないとかモチベーションが上がらないという精神的なダメージが大きくなってしまいます。
夏バテで食欲が低下すると、さっぱりしたものしか食べたくなくなったり、冷たいものばかりが飲みたくなってしまいます。
これは、自律神経がバランスを崩すことによって起こる症状です。
こうした夏バテは、主に激しい温度差に体が適応できないことが原因となります。
真夏には、屋外は高温多湿な環境で、室内では冷房が効いていて快適です。
大きな温度差を行き来すると、体内の自律神経がどちらの環境に合わせたら良いのか分からなくなってバランスを崩してしまうのです。
自律神経は全身のあらゆる機能をつかさどっているため、バランスが崩れると消化機能が低下して食欲がなくなったり、睡眠のリズムや質が悪くなって疲れが抜けにくくなります。
夏バテは迅速に解消するべし
たかが夏バテ、されど夏バテです。
夏バテは、放置していても涼しい秋が到来すれば自然に治癒できると以前では考えられていました。
確かに大きな気温差に体が適応できないことが原因で起こる夏バテなら、気温差がそれほど大きくない秋がくれば、特に何もしなくてもトラブルは解消するかもしれません。
しかし夏バテが長引くと、やる気が出ずに集中力にかけるなど、日常生活にもマイナスの影響が出てしまいます。
特に仕事や勉強で集中しなければいけない人にとって、これは大きな機会損失ではないでしょうか。
また、夏には紫外線を多く浴びるため、体内で活性酸素が大量に作られやすい環境となります。
活性酸素は疲労やストレスを感じた時にも作られるもので、体内に蓄積されると酸化ストレスと呼ばれるストレスレベルが高くなってしまいます。
夏バテが長引くと酸化ストレスのレベルもどんどん高くなってしまうので、注意が必要でしょう。
もしも夏バテかもしれないと感じたら、まずは不安定な自律神経を安定させるためにゆっくりと体を休めたり、室内外の温度差をできるだけ減らすためにエアコンの設定温度を高めるなど、できることから始めましょう。
ストレッチをして、全身の神経や筋肉に程よい刺激を与えることも効果的です。
ただし、やり過ぎると汗をかいて脱水症状が起こりやすいですし、体温が高くなりすぎると汗量が増えてかえって逆効果です。
そのため、適度なストレッチに留めておくことがポイントです。